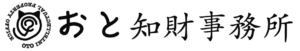カラオケボックス


解説
要は音源を作った人の権利なんじゃよ
著作権法でレコードは「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したものをいう」と定義されています(著作権法第2条1項5号)。要は音が固定されているものなら、レコードじゃなくても、ハードディスクとかUSBメモリーとかでもよいわけです。
そしてレコード製作者は「レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう」です(著作権法第2条1項6号)。何か音が固定されている媒体があったら、その媒体に音を最初に固定した人がレコード製作者です。
カラオケ音源作った人にも発生する
カラオケに限られず、既成曲を打込みで再現した人もレコード製作者です(もちろん楽曲の著作権は別ですよ)。同じく著作隣接権である実演家にもなります(著作権法89条1項、2項)。DTMやってる人は知らないうちに実演家、レコード製作者になっているのではないでしょうか。
余談ですが、J-POP等の既成曲が搭載されている電子キーボードがあります。搭載されている楽曲のデータ作成は外部の打込み職人さんに発注することが多いです。その場合、打込み職人さんに発生するのはレコード製作者の権利(と実演家の権利)なので、著作権じゃなくて著作隣接権なんですよね。だから委託契約書には「著作権を譲渡する」じゃなくて「著作隣接権を譲渡する」って書かないといけない。
原曲を耳コピして…打込みで作っていく
DTMをやってる方ならこれがどんだけ大変な作業かお判りいただけると思います。
SMF系のMIDIカラオケなら間違いなく、この方法で作成されます。最近はオーディオカラオケも多くなっていますが、フルバンド演奏を録音して作るのはお金がかかるので、打込みとオーディオ演奏入力の合わせ技をDAWで編集して作っているのではないかと想像します(未確認)。→カラオケ制作会社にスタジオがあって、そこで生録音しているそうです。
訴えられた人もおる
平成28年(ワ)第34083号 著作隣接権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/086410_hanrei.pdf
カラオケボックスで撮った動画をYouTubeにアップした人をDAMの第一興商さんが訴えました。
裁判のときにはすでにYouTubeの動画は削除していたのですが、それだけでは許してもらえずスマホに残ってる動画も削除しろとの判決が出ました(正確には「同記録が入力されている被告の占有に係るハードディスクその他の記録媒体から消去せよ」です)。
著作隣接権の侵害であることは一目瞭然だったので、判決文めちゃめちゃ短いです。